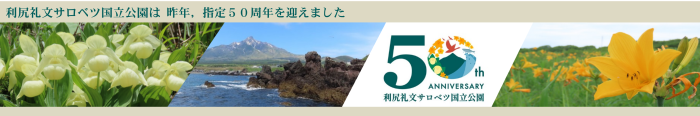アクティブ・レンジャー日記 [北海道地区]
真冬の浜頓別クッチャロ湖
2025年01月24日
稚内
こんにちは! 礼文とクッチャロ湖担当アクティブ・レンジャー(AR)の後澤です。
クッチャロ湖は,湖とその周辺湿地が渡り鳥の集団渡来地として国指定鳥獣保護区に指定されているとともに,ラムサール条約(正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)に日本で3番目に登録されています。渡り鳥の中でも特に,日本で越冬するコハクチョウのほとんどが中継地として飛来する重要な場所です。
湖のほとりには,ラムサール条約湿地の価値を広く知ってもらうための教育・普及啓発施設として建てられた〈浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館〉があります。水鳥観察館のパンフレットによれば,コハクチョウの渡りのピークは4月と10月で,春のピーク時には約6,000羽が集まるそうです。
秋の渡りが終わると,クッチャロ湖は氷に覆われ始め,12月下旬になると湖の大部分は凍ってしまいます。しかし,一部のハクチョウは南に渡らずに,冬の間もクッチャロ湖に留まっています。水鳥観察館の千田さん(浜頓別町役場職員)のお話では,今年は約200羽のハクチョウが越冬しているそうです。
クッチャロ湖は,湖とその周辺湿地が渡り鳥の集団渡来地として国指定鳥獣保護区に指定されているとともに,ラムサール条約(正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)に日本で3番目に登録されています。渡り鳥の中でも特に,日本で越冬するコハクチョウのほとんどが中継地として飛来する重要な場所です。
湖のほとりには,ラムサール条約湿地の価値を広く知ってもらうための教育・普及啓発施設として建てられた〈浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館〉があります。水鳥観察館のパンフレットによれば,コハクチョウの渡りのピークは4月と10月で,春のピーク時には約6,000羽が集まるそうです。
秋の渡りが終わると,クッチャロ湖は氷に覆われ始め,12月下旬になると湖の大部分は凍ってしまいます。しかし,一部のハクチョウは南に渡らずに,冬の間もクッチャロ湖に留まっています。水鳥観察館の千田さん(浜頓別町役場職員)のお話では,今年は約200羽のハクチョウが越冬しているそうです。

越冬するハクチョウたちのために,千田さんを中心とした浜頓別町役場職員の方が毎日1回,胴付き長靴(胸元まで及ぶゴム製の防水ブーツ)を身につけ,給餌を行っています。


ハクチョウへの給餌は,当初は春と秋の渡りの時期に限って行われていました。当時は冬期に湖が全面結氷し,そのため越冬するハクチョウはいなかったそうです。ところが,今から約50年前の昭和40年代に,春に早く渡ってきたハクチョウが厳寒のために湖や川が全面凍結して水草を食べられなくなり,餓死してしまうことがありました。見るに見かねて茶殻を給餌したことから冬の給餌が始まったそうです。しかし,このことでハクチョウが越冬するようになったわけではありません。
実際にハクチョウがクッチャロ湖で越冬するようになったのは,今から38年前の昭和62年頃からだそうです。クッチャロ湖が汽水湖(淡水と海水が入り混じる湖)で,海とつながるクッチャロ川の河口拡張によって海水の流入量が増し,塩分濃度が高くなったことに加え,地球温暖化により湖が全面氷結しなくなったためと考えられています。
このように,環境の変化によってハクチョウたちが越冬するようになったそうです。
ここにも人の営みや温暖化の影響が現れていたのですね。
水鳥観察館前にも,次の写真のように,湧水の流入によって冬の間水面が凍ることなく残っているエリアがあります。
ここで給餌が行われ,ハクチョウ類やカモ類の生活場所となっています。
実際にハクチョウがクッチャロ湖で越冬するようになったのは,今から38年前の昭和62年頃からだそうです。クッチャロ湖が汽水湖(淡水と海水が入り混じる湖)で,海とつながるクッチャロ川の河口拡張によって海水の流入量が増し,塩分濃度が高くなったことに加え,地球温暖化により湖が全面氷結しなくなったためと考えられています。
このように,環境の変化によってハクチョウたちが越冬するようになったそうです。
ここにも人の営みや温暖化の影響が現れていたのですね。
水鳥観察館前にも,次の写真のように,湧水の流入によって冬の間水面が凍ることなく残っているエリアがあります。
ここで給餌が行われ,ハクチョウ類やカモ類の生活場所となっています。

ところで,ハクチョウたちは24時間このエリアにいるわけではありません。このエリアは岸に隣接しているため,夜間にキタキツネに襲われる危険が大きいそうです。そのため,夜間は近くのクッチャロ川や頓別川などの水辺に近い氷の上で過ごし,明るくなるとこのエリアにやってきます。
ハクチョウたちがこのエリアに飛来する姿を撮影したくて,休日に何度か通ってみました。ところが,訪れる度にハクチョウたちが現れる時刻・飛び去る時刻が違うのです。そのため,クッチャロ湖に着いたときには既にハクチョウが飛来した後だったり,それならば飛び去るところを撮ろうと日没までねばっても飛び立たなかったり,なかなかチャンスが捉えられません。
水鳥観察館の千田さんにお聞きしたところ,その時刻は天候や気温によって大きく変わり,天気が良いと早い時刻からやって来て,遅い時刻まで居る,逆に天気が悪いと遅い時刻にやって来て,午後も早い時刻に飛び去るそうです。晴れた穏やかな日に,早朝から待つのがよいのでしょうか。チャレンジしてみたいと思います。
ハクチョウたちがこのエリアに飛来する姿を撮影したくて,休日に何度か通ってみました。ところが,訪れる度にハクチョウたちが現れる時刻・飛び去る時刻が違うのです。そのため,クッチャロ湖に着いたときには既にハクチョウが飛来した後だったり,それならば飛び去るところを撮ろうと日没までねばっても飛び立たなかったり,なかなかチャンスが捉えられません。
水鳥観察館の千田さんにお聞きしたところ,その時刻は天候や気温によって大きく変わり,天気が良いと早い時刻からやって来て,遅い時刻まで居る,逆に天気が悪いと遅い時刻にやって来て,午後も早い時刻に飛び去るそうです。晴れた穏やかな日に,早朝から待つのがよいのでしょうか。チャレンジしてみたいと思います。

ハクチョウたちが厳冬のクッチャロ湖で越冬するようになった経緯や,地域の方々によって長い年月にわたり支えられてきたことがわかりました。ハクチョウたちがいるクッチャロ湖の真冬の景色がこれからもずっと続いていってほしいと願っています。